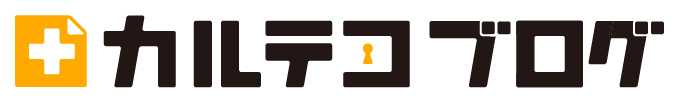「整える」は、動物が先にやっていた
近年、「自律神経を整える」という言葉を耳にする機会が増えています。
深呼吸、ヨガ、マインドフルネスなど、人は心身のバランスを保つためにさまざまな方法を試してきました。
一方で、自然界の動物は特別な道具がなくても、環境に合わせて穏やかに過ごし、結果として心身のリズムを保っています。
動物の行動を観察すると、人が忘れかけている自然のリズムや知恵が見えてきます。
ゴリラはストレスで下痢しやすい──腸は「心の鏡」
力強いイメージのあるゴリラですが、実際には繊細な一面があります。
群れの入れ替わりや騒音など、環境の変化が続くと体調に変化が表れることがあります。その一例が下痢です。
飼育下では糞中コルチコイド(ストレスの指標)を非侵襲的に測定し、来園者数や展示環境の違いが数値に与える影響を調べる研究が行われています。ストレス反応を客観的に追跡する取り組みです。
ストレスを感じた後のゴリラは、静かな場所に移動してしばらく過ごすことがあります。
刺激から距離を取り、自然と落ち着きを取り戻す行動です。
人も同様に、刺激が続いたときにスマートフォンを置いて静かな空間に身を置くだけで気分が和らぐことがあります。静けさは回復のための時間ともいえるでしょう。
犬の「あくび」と深呼吸──呼吸でリズムを戻す
犬が緊張時に見せる「あくび」は、眠気だけでなく気持ちを切り替えるしぐさとして観察されます。
大きく息を吐く動きは体を落ち着かせる方向に働くと考えられます。
人でも、緊張のあとに深いため息が出ることがあります。これも体が自然にリズムを整えようとする反応のひとつです。
ゾウの水浴び──熱と気分のクールダウン
ゾウの水浴びや泥浴びは、体温の調整や皮膚の保護のために行われます。乾燥地帯に生息する個体ほど、日常的にこの行動をとる傾向があります。
水や泥を浴びることで体表面の温度を下げ、乾燥や虫から肌を守る効果もあります。
体温が下がると気持ちも落ち着きやすくなります。
人もぬるめの湯に浸かって一日の高ぶりを鎮め、入浴後の体温リズムで休息に入りやすくなります。
鳥の羽づくろい──「整える」を体現する動作
鳥の羽づくろいは、汚れを落とすだけでなくコンフォート行動(身づくろい行動)として知られています。
落ち着いた環境で多く見られ、撹乱の直後には気分を落ち着かせるしぐさとして現れることもあります。
安心しているときに多く見られる行動で、「整える」という感覚を象徴しています。
人でも、デスクを片づけたり髪をとかしたりすると気分がすっきりすることがあります。
猫の日向ぼっこ──光でリズムを整える
猫が日向ぼっこを好むのは、暖かさだけが理由ではありません。
朝の光は体内時計のリセットに関わり、夜のメラトニン分泌や体温リズムを整える役割を持ちます。脳内のセロトニン系とも関連し、気分と覚醒のリズムを維持する働きがあります。
人も朝日を浴びることで体内時計が整いやすくなります。カーテンを開けて自然光を感じるだけでも、一日の始まりが軽やかになります。
馬の群れとゆるやかな同調──つながりが安心を生む
草を食べるテンポや向きがそろうなど、群れの馬にはゆるやかな同調が見られます。
仲間が近くにいることで安心し、落ち着く様子が観察されています。
社会的なつながりとストレス反応の関係は、動物行動学の研究でも示唆されています。
人でも、家族や仲間と静かに同じ空間で過ごすと呼吸や動作のリズムが自然に合い、安心感が高まることがあります。
ペンギンの寄り添い──温もりは緊張を和らげる
ペンギンが身を寄せ合う行動は、寒さをしのぐ目的がよく知られています。
同時に、寄り添うことで動きが穏やかになり、群れ全体の安定に寄与することもあります。
人でも、ハグや肩を寄せるだけで気持ちが落ち着くことがあります。ふれあいは安心感を高める大切なコミュニケーションです。
ヘビの「じっと動かない」──静けさという戦略
ヘビが動かないのは、怯えているからとは限りません。
待ち伏せ型の捕食では「気づかれにくい」ことが有利で、動きを抑えるほど獲物や外敵に見つかりにくくなります。
また、変温動物であるヘビは外環境に体温を委ねているため、不要な動きを減らすことがエネルギー節約につながります。
寒いときは体を丸めて熱を保ち、暑いときは岩陰や水辺で熱を逃がすなど、「環境を借りて整える」行動をとります。
人も疲れを感じたとき、何もしない時間を取るだけで回復することがあります。動かないことは怠けではなく、整えるための選択にもなります。
クジラの歌──リズムが落ち着きを生む
クジラの鳴き声(ホエールソング)は、繁殖期のコミュニケーションに関わるとされ、長いフレーズが海中に一定のリズムを生み出します。
群れの行動と関係している可能性も指摘されています。
人でも、鼻歌やハミングのように一定のリズムで声を出すと呼吸が整い、落ち着きやすくなります。音のリズムは、環境の「ゆらぎ」として安心をもたらす要素です。
まとめ:動物は本能的に「整える」行動をとっている
動物は「整えよう」と意識しているわけではありませんが、結果として心身のバランスを保つ行動をとっています。
ゴリラは静かな場所に退避し、猫は朝の光を浴び、海の哺乳類は一定のリズムでコミュニケーションを行います。
多くの行動は、体温調節やストレス反応、社会的関係の維持といった生理的・社会的な仕組みで説明できます。
人も、光、呼吸、静けさ、つながりといった基本的な要素を意識するだけで、日常の中でリズムを整えやすくなります。
タグ:自律神経, ストレスケア, 動物行動, セルフケア, 光とリズム, マインドフルネス
参考文献・出典
- 黒野 裕史「動物介在活動に従事する動物の内分泌的指標を用いたストレス研究」修士論文, 酪農学園大学, 2018.
- 岩本 杏「人の活動は野生動物にとってストレスなのか? 高尾山ムササビ‐糞中コルチゾール代謝産物を用いた評価」日本動物学雑誌, 2021.
- 永澤美保・菊水健史「オキシトシンと視線との正のループによるヒトとイヌとの絆」Science, 2015.
- 日本農業研究機構(NARO)「動物行動管理グループ」紹介.
- 東京大学「哺乳類におけるケミカルコミュニケーションに関する研究」.
- 日本大学 農学部「動物のもつ力の行動学的究明」.
- 日本学術会議「情動をうみだす脳と身体の協働システム」紹介.
- 理化学研究所「臓器を個別に制御する自律神経の仕組みを解明(マウス)」プレスリリース, 2024.
- 補助:Radar-Based Respiratory Measurement of a Rhesus Monkey by Suppressing Nonperiodic Body Motion Components, arXiv, 2023.