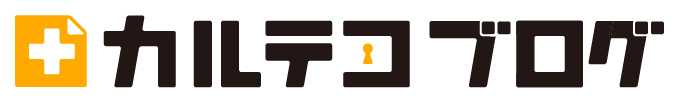9月なのに夏のように暑い、と思ったことはありませんか?
そんな季節に増えるのが「秋バテ」と呼ばれる不調です。
昔は、夏が終わればすぐに秋の気配を感じました。朝晩の空気が少しひんやりして、金木犀の香りがふっと漂い、長袖を出す合図になる――そんな小さな合図を、体は正確に受け取っていた気がします。けれどここ数年、九月になっても真夏日が続き、十月でも汗ばむ午後があります。ようやく秋だと思えば、急ぎ足の冬が追い越していく。季節の歩幅が合わず、体も心も置いてけぼりになりがちです。
この体感は勘違いではありません。観測データでも、日本の平均気温は長期的に上昇傾向にあり、近年も記録的に高い年が複数みられます。都市部ではヒートアイランドの影響も加わり、体感の暑さが強まりやすい環境が重なっています。結果として、夏の長期化や季節の後ろ倒しが起き、秋バテのような季節特有の体調不調を意識する場面が増えてきました。
季節の変わり目には、だるさやめまい、頭痛、冷えといった不調が見られることがあります。こうした不調について理解を深めておくと、自分に合った生活習慣の工夫やセルフケアを考えるきっかけになります。
日本の「四季」が「五季」に?秋バテが生まれる背景
夏が長引き、秋が短くなる現象
夏の暑さが長引き、秋の涼しさが短く感じられることは、多くの人が実感している現象です。日中はまだ汗ばむほどの暑さがある一方で、朝晩は涼しくなる――こうした気温差は体調の切り替えを難しくし、「秋バテ」と呼ばれる不調を意識する人も増えているとされます。
「夏の長期化」のダメージが体に蓄積して、急に秋になると体は季節の変化についていけないことがあります。
かつては「お盆を過ぎると涼しくなる」といった文化的な感覚がありましたが、近年は9月に入っても真夏日が続く地域があり、統計的にも高温傾向が指摘されています。その結果、秋らしい快適な気候が短く、すぐに冬の寒さへ移行するように感じられるケースもあります。
こうした「夏の長期化」と「秋の短縮化」により、四季の切り替えがスムーズにいかず、心身のリズムを崩しやすいと考えられます。生活の中でも、春・夏・秋・冬の四季に加えて“残暑の季節”をひとつの独立した時期として意識することが、体調管理の目安になりつつあります。

気候データから見る「五季化」
気象庁のデータを見ても、平均気温の上昇や季節のずれは確かに進んでいます。東京では1970年代と比べて真夏日が増え、9月に入っても30℃を超える日が珍しくありません。
こうした背景から、「春・夏・秋・冬」という四季がはっきりしなくなり、「夏 → 残暑 → 短い秋 → 冬」と、まるで“五つの季節”を過ごしているように感じる人が増えています。
さらに、暑さを判断するWBGT(暑さ指数)では、28℃を超えると「厳重警戒」とされ、屋外での活動に注意が必要とされています。9月以降もこうした気温の日が続くことで、暮らしの中で「夏の延長線」を意識せざるを得なくなっているのです。
「五季化」という言葉は正式な学術用語ではありませんが、生活者が日々の体感から名付けた“実感のことば”として広がりつつあります。季節が曖昧に移ろう中で、体のリズムが追いつかず、だるさや疲れを感じる人が増えているのも自然なことかもしれません。

引用元(出典)
気象庁「過去の気象データ検索(東京・月ごとの値:1970年)」
https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/monthly_s1.php?prec_no=44&block_no=47662&year=1970&month=&day=&view=a2
気象庁「過去の気象データ検索(東京・月ごとの値:2024年)」
https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/monthly_s1.php?prec_no=44&block_no=47662&year=2024&month=&day=&view=a2
気候データから見る「五季化」
大都市では真夏日日数の増加傾向が明確で、夏の終わりの残暑が長引くため、昼夜の寒暖差が強く出ます。こうした「五季化」は、単なる表現ではなく、生活者の症状(だるい・頭痛・めまい・冷え)の増加という形でも現れます。移行時期を“もうひとつの季節”として扱い、生活と対策を段階的に切り替えることが予防の第一歩です。
また、暑さの負担は気温だけでは判断できません。湿度や日射の影響を含む暑さ指数(WBGT)を目安に、屋外活動・運動の時期と強度を調整するのも賢い対策です。WBGTが28を超える日は熱負荷が高く、秋口でも油断は禁物。こまめな飲み物の補給や休憩が予防と解消につながります。
環境省:暑さ指数(WBGT)の意味・目安
https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php
環境省:暑さ指数(WBGT)の解説ページ
https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_info.php
環境省:暑さ指数(WBGT)予測情報(翌日以降)
https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_forecast.php
季節の変わり目に体調を崩しやすい理由|秋バテの起きやすさ
急な気温差と自律神経の乱れ
季節の変わり目の不調の原因のひとつは、急な寒暖差です。体は自律神経で体温を微調整しますが、気温の上下が大きい時期は負荷が増え、だるさ・頭痛・めまい・肩こりなどの症状が出やすくなります。休み明けや活動量が急に増える時期も負担が重なります。
睡眠・消化・ホルモンへの波及
自律神経の乱れは、夜の睡眠の質や日中の食欲、ホルモン分泌のリズムに影響すると考えられています。眠りが浅いと疲れが残りやすく、翌日にだるさや頭痛を感じる人も少なくありません。
また、疲労やストレスがたまると消化の働きが落ち着かず、冷たい飲み物や甘いものに手が伸びやすいと感じるケースもあるようです。
こうしたときには、朝の光を浴びて体内リズムを意識的に整えたり、軽い運動や入浴でリラックスしたり、寝室の温度や湿度を快適に保つ工夫が役立つといわれています。これらを取り入れることで、心身のリズムを意識しやすくなるでしょう。
「秋バテ」とは?|季節の変わり目に増える不調
秋バテの“出やすい時期”の目安
秋バテは、一般にお盆明けから9月〜10月のはじめ頃にかけて意識されやすいと言われます。気温は下がっても湿度が高い日や、昼と朝晩の寒暖差が大きい日は負担を感じやすく、秋バテへの注意が高まります。
秋バテの原因(長引く暑さ・寒暖差・冷房疲れ)
「秋バテ」は医学的な病名ではなく、正式な診断基準もありません。一般的には、夏の暑さによる疲れが残ったまま秋を迎えたときに感じやすい体の不調を指す俗称として使われています。残暑による熱負荷、朝晩の寒暖差、空調による冷えや乾燥などが重なると、自律神経の切り替えがうまくいかず、だるさ、浅い眠り、食欲の低下などにつながることがあります。
こうした時期には、生活リズムを整えたり、休養をしっかり確保したりといった工夫が、快適に過ごすためのヒントになるでしょう。
季節の変わり目にひそむ「秋バテ」 ✅
夏の暑さがようやく落ち着いたと思ったら、なんとなく体がだるい。食欲もいまひとつ…。そんなときに耳にするのが「秋バテ」という言葉です。
夏の疲れと秋の気候の変化が重なって体調を崩す様子を、わかりやすく表現した“生活の知恵ことば”のひとつです。正式な病名ではありませんが、季節の変わり目に多くの人が経験する不調を的確に言い表しているため、広く使われています。
こんなサインに心当たりはありませんか?
秋バテのチェックリスト で確認してみましょう。

上手につきあうコツ
大切なのは「気のせい」で片づけないこと。季節の変わり目は体が環境に適応するのにエネルギーを使うため、普段よりも疲れやすくなります。意識的に休養をとったり、生活リズムを整えたりするだけで、ぐっとラクになることも。
もし症状が長引くときは、自己判断せずに医療機関に相談することも忘れずに。
「四季」から「五季」へ|これまでとこれからの体調管理
従来の四季型の健康管理(ビフォー)
従来の健康情報では、四季ごとに注意すべき不調があるとされてきました。
たとえば、春は花粉症、夏は熱中症や夏バテ、秋は空気の乾燥、冬は風邪やインフルエンザといったように、季節ごとに代表的な体調リスクが語られてきたのです。
このように、季節に応じて健康リスクが切り替わるという“暮らしの経験則”が、多くの人の健康管理の前提となっていました。
五季化時代の健康管理(アフター)
近年は「残暑から初秋」にかけての移行が長引き、気温差や湿度変動による自律神経の乱れ、夏の疲労が残ること、食欲不振などが重なり、いわゆる「秋バテ」と呼ばれる不調が出やすいとされています。厚生労働省関連サイトや医療機関でも、これは医学的な病名ではなく、複合的な要因による体調不良の俗称として紹介されています。
そのため、従来の「秋=乾燥対策」というイメージだけでなく、8月後半頃から睡眠リズムを整える、冷たい飲食を控えるなど、季節の切り替わりに向けた生活リズムの調整を少し早めに取り入れる工夫が役立つ場面もあります。
季節の変わり目・秋バテを乗り切るセルフケア(詳解)
① 食事|温かい汁物と旬の食材を“取り入れやすくする”工夫
移行時期は体調の変化を感じやすいため、まずは“温かい”食の工夫から始めるのがおすすめです。味噌汁やスープに根菜・きのこ・大豆などを加えると、冷たい飲み物の摂り過ぎを見直すきっかけになります。規則的な食事は生活リズムの維持に役立つとされ、日中の過ごしやすさにつながることがあります。
② 睡眠:環境×生活習慣の二段構え
良い睡眠には、寝室の温湿度・光・音といった環境と、朝の光・軽い運動・入浴などの生活習慣の両方が関わります。秋口は日中暑く夜に冷えやすい時期なので、寝具や室温をその日の気候に合わせて調整することが大切です。こうした工夫は、心地よい眠りにつながり、翌日の過ごしやすさを支える一因となります。
③ 軽い運動:ウォーキング+ストレッチで“血流とリズム”
体調管理のための運動は、高強度に限る必要はありません。無理のない中等度の活動(速歩など)を週合計で積み重ねたり、日常の歩行や家事といった軽い活動を少しずつ増やすことも、健康維持の一助になります。朝〜日中には短時間のウォーキングやこまめな歩行を取り入れ、夕方にはストレッチなどで体をゆるめると、気分転換やリラックスにつながると感じる人もいます。その日の体調や体力に合わせて強度や時間を調整し、痛みや不調がある場合は無理をしないことを基本にしましょう。
④ 室内環境:WBGTも“家の中”を意識
「気温は下がったのに湿度が高い」時期は、体の熱放散が進まずだるさが長引きます。除湿・送風・サーキュレーターで空気を回し、エアコンは“冷やす”より“湿度管理”。屋外活動はWBGTを目安に、28以上なら強度を落とすのが堅実な対策であり予防策です。
よくある質問(FAQ)
Q. 「秋バテ」と「夏バテ」の違いは?
夏バテは高温多湿の熱負荷、秋バテは寒暖差と切替え時期の自律神経の乱れが中心。どちらも症状は共通し、対策は「睡眠・運動・温かい食事・適切な飲み物」が基本で、予防と解消の両方に役立ちます。
Q. どの時期に対策を始めればいい?
目安は「お盆後〜九月のはじめ」。この時期からは、冷たい飲み物や食べ物を摂りすぎないようにしたり、就寝・起床時間を整えるなどの工夫が大切です。こうした生活リズムを意識することで、秋口に感じやすい体のだるさに対して、より快適に過ごしやすくなる人もいます。
Q. 食べやすい食べ物・おすすめの飲み物は?
飲み物は、冷たいものばかりに偏らず、常温や温かいお茶、白湯などを選ぶ人も多いようです。体を冷やしにくく、日常に取り入れやすい工夫としておすすめされることがあります。
汗をかいたときには、水分だけでなく塩分やミネラルを一緒にとることを意識するとバランスがとりやすいでしょう。
また、カフェインのとり方もポイント。夕方以降は控えめにすると、夜の休息がスムーズになりやすいといわれています。
Q. 秋バテはどれくらい続く?
個人差はありますが、残暑の落ち着きや活動量の変化とともに和らいでいくことが多いと言われます。長く続く不調が気になる場合は、無理をせず休養を確保し、必要に応じて医療機関へ相談してください。
Q. 秋バテのとき、無理に運動しない方がいい?
体調に合わせて強度を調整することが大切です。秋バテを感じやすい時期には、短時間のウォーキングやストレッチなど、無理のない範囲の運動を取り入れることがひとつの工夫になります。
まとめ|「秋バテ」は“季節のズレ”に気づくサイン
ここ数年は「四季」では語れないほど季節のリズムが変化し、残暑の長期化や急な気温差が体に負担をかけています。そんな環境の変化を表す生活の知恵ことばが「秋バテ」です。
正式な病名ではなくても、多くの人が実感している“季節のサイン”。だるさや食欲不振、浅い眠りを「気のせい」と片づけず、生活リズムや食事・睡眠・運動を少し調整するだけで、ぐっとラクに過ごせることがあります。
秋バテ対策は、健康管理の新しい季節感=「五季化時代」のセルフケアの第一歩。もし不調が続くときには、無理せず休養をとり、必要に応じて医療機関に相談することも忘れずに。
主な出典(本文に各所で引用)
- 気象庁:2024年の日本の年平均気温は統計開始以来最高/上昇率
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/2024/ann_warmest.html - 気象庁:大都市の真夏日日数の長期変化(東京ほか)
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/view/maxtemp_month.html - 気象庁(東京ローカル):東京の月平均気温と最高気温日数(真夏日・熱帯夜の増加傾向)
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/monthly_s3.php?prec_no=44&block_no=47662 - 環境省:暑さ指数(WBGT)の意味・目安
https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php - 環境省:暑さ指数(WBGT)の解説ページ
https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_info.php - 環境省:暑さ指数(WBGT)予測情報(翌日以降)
https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_forecast.php - 文部科学省:学校における熱中症事故防止について(暑熱順化や休み明けの配慮)
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/013_index/toushin/__icsFiles/afieldfile/2021/07/16/1412722_02.pdf - 厚生労働省:e-ヘルスネット「睡眠と生活習慣」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-001.html - 厚生労働省:e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-002.html - 厚生労働省:e-ヘルスネット「睡眠不足と自律神経」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-003.html